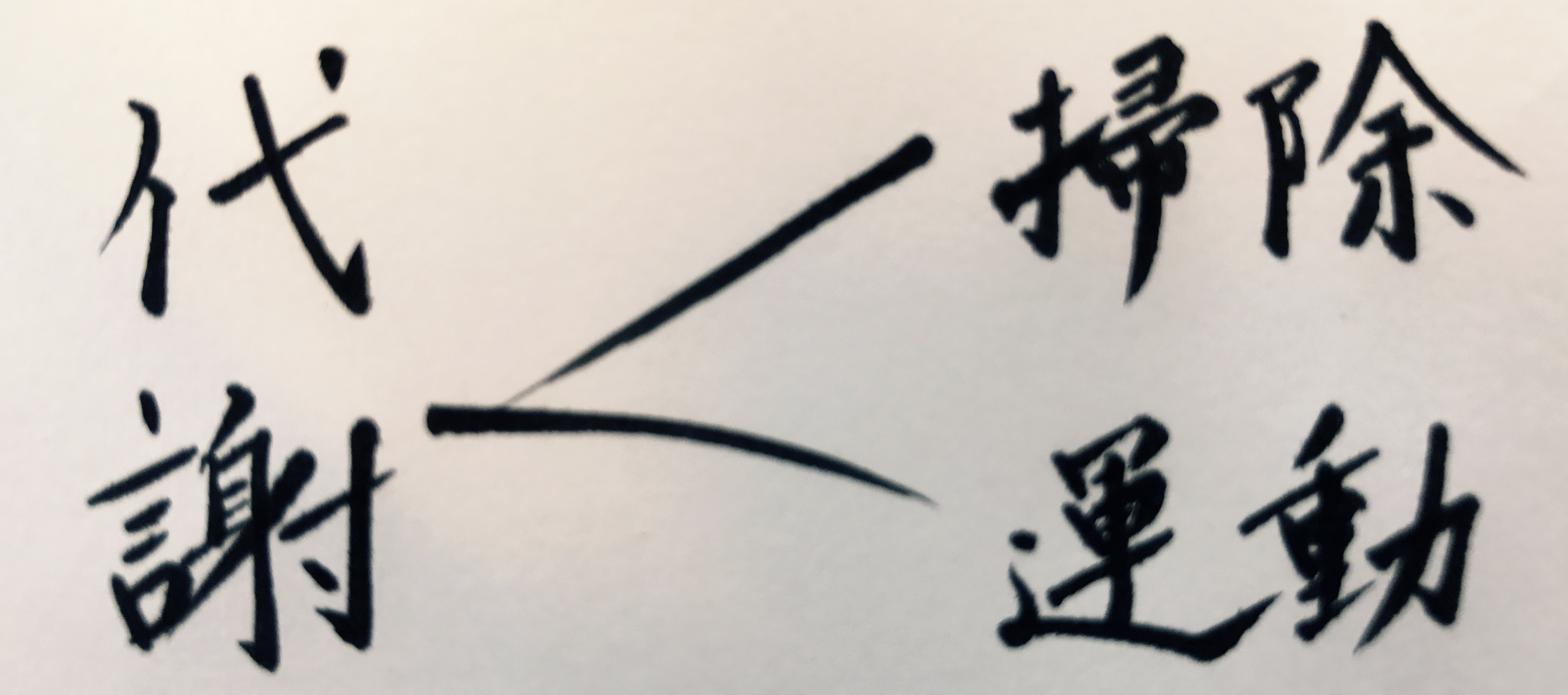
今回は新陳代謝についての現段階の考察を記します。
「代謝」とは「食べたものや飲んだものが、体の中で生きるエネルギーとして正常に転化されているか、またそのスピードや質のこと」、と定義します。
代謝がいい状態とは、川に例えると綺麗に透き通ったお水が体内をさらさらと流れている状態です。普段から体は軽いですし、風邪気味になってもどこかしら痛みがあっても、気のめぐりがいいので痛みのひきも治りも早くなります。代謝がよくない状態とは、濁った泥泥のお水が体内を流れている状態。風邪は引きやすいですし、慢性的な体の重さを感じたり、治癒にも時間がかかります。
さて、代謝のスピードや質を決めているのは主に「掃除」と「運動」の2つになりますが、運動よりも代謝の土台となる「掃除」について述べてみます。「代謝をあげるにはまず運動でしょ、なぜ掃除なの?」という声が聞こえてきそうですが、この理由について記します。
家にあるすべてのモノは、自分の心と1つずつ見えない糸でつながっています。玄関に12足の靴があれば24本の糸と、冷蔵庫に40個のモノが入っていれば40本の糸と、本が100冊あれば100本の糸と、洋服が25着あれば25本の糸とつながっています。普段大切に使っているモノであればその糸はピンと張って生きているのですが、使っていないモノ(=ガラクタ)に囲まれていると心とそのモノがつながっている糸の張りが弱まり、体にまとわりついてくるのです。このまとわりついた糸の束が理由で運動したり、行動しようというエネルギーにブレーキがかかりますし、体の重みが増し、体のエネルギーの循環が滞ってくることで、代謝が悪くなってきます。
ここでいう「掃除」とは「使わないものを徹底的に捨てる」ということです。「迷ったら捨てる」です。その結果、自分にとって本当に必要なエネルギーだけが残ってきます。幾重にも重ねられたモノや床に直接置かれていたモノが減ってくると、本来そのモノに宿っているエネルギー(魂、ともいう)が回復してきますので、部屋全体のエネルギーもあがってきます。この空間に住んでいる人もそのエネルギーを受けてエネルギーが高まり、そのおかげで代謝が高まります。
目に見えない世界のことで科学で証明されていることでもないですが、掃除が人体に及ぼす影響というのはことばにするとこういうものだと考えています。本来氣を休める場所である家が自身の氣を奪ってしまう場所にしてしまうのはあまりにもったいないことです。
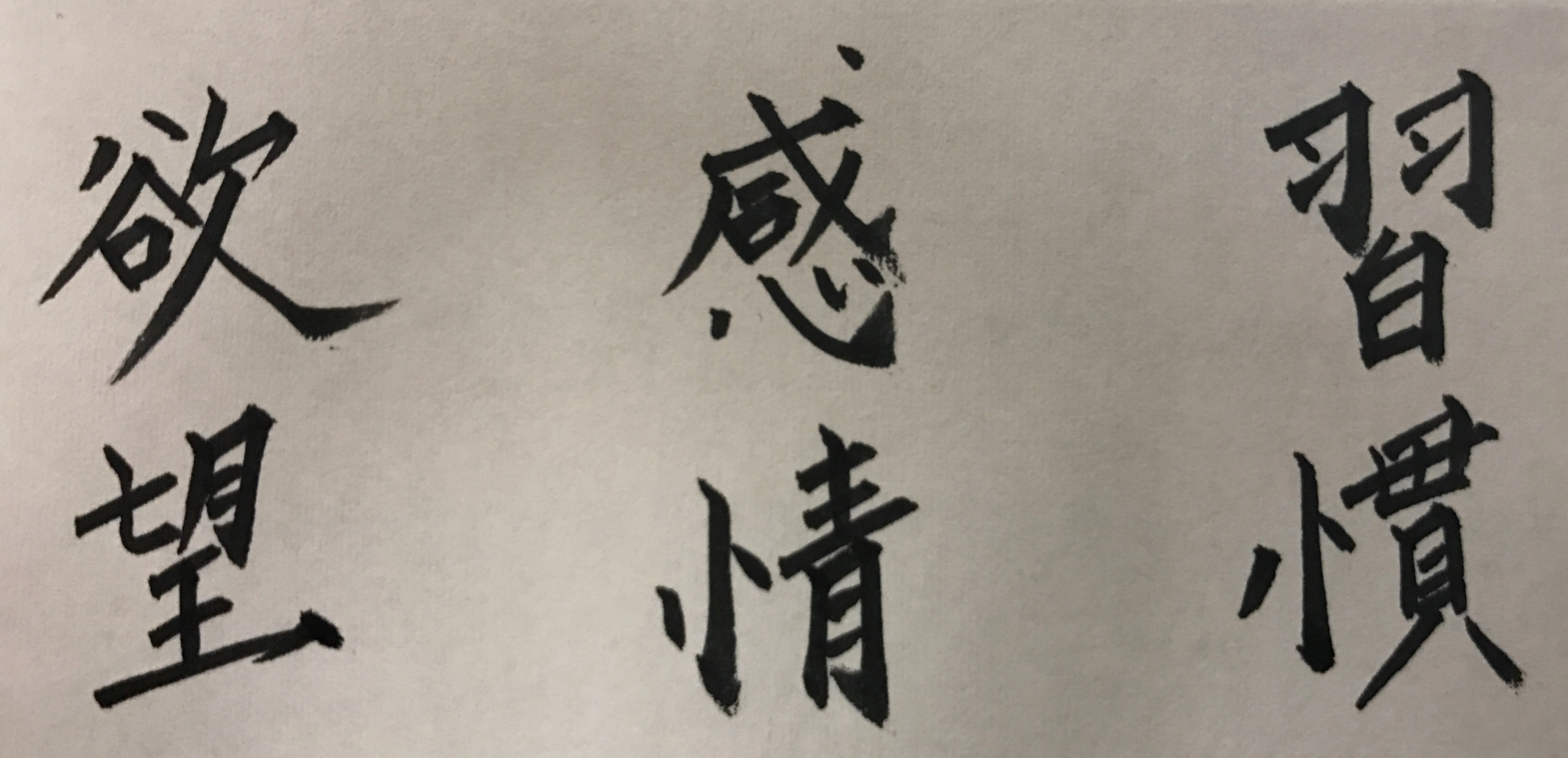

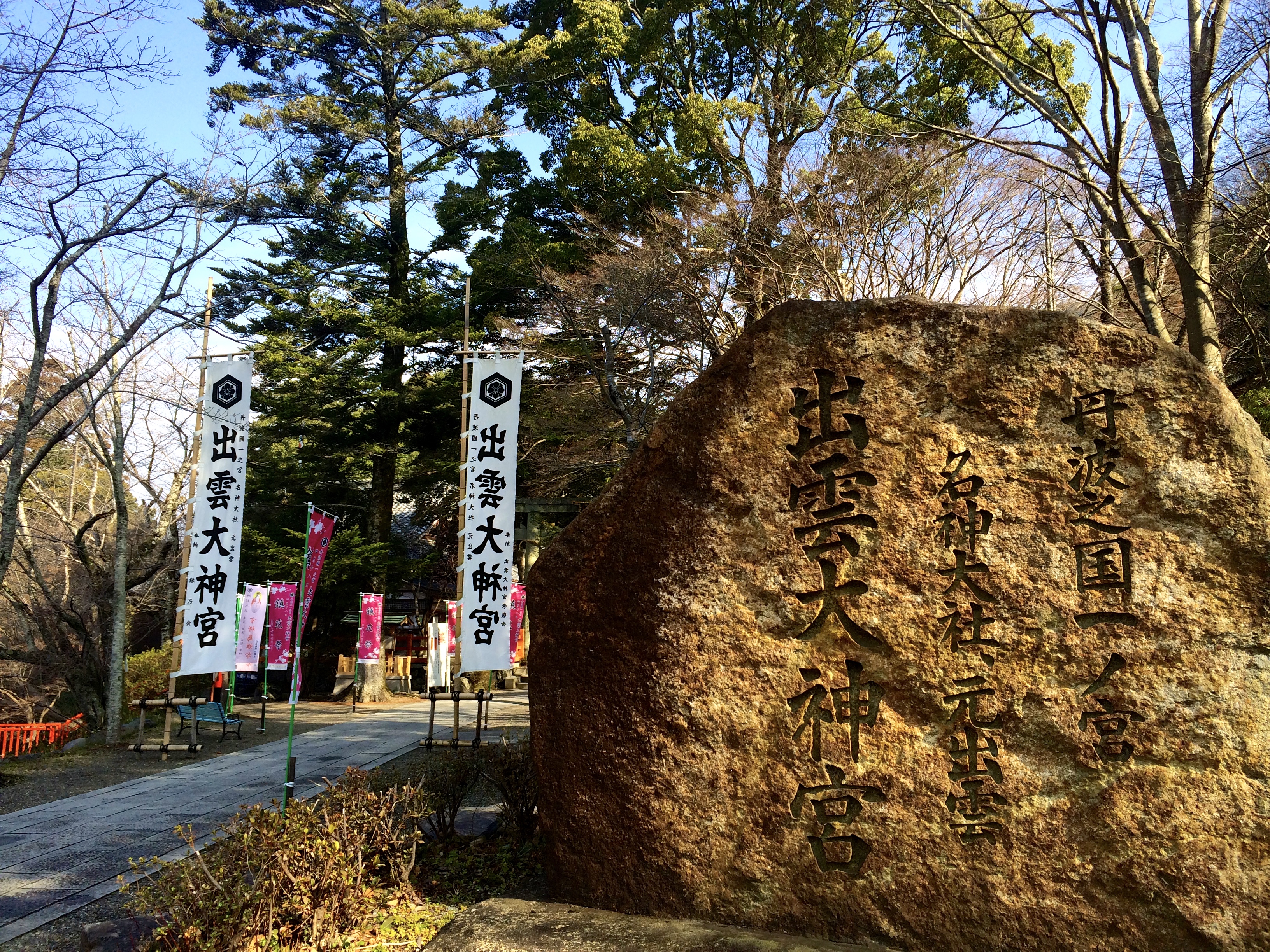

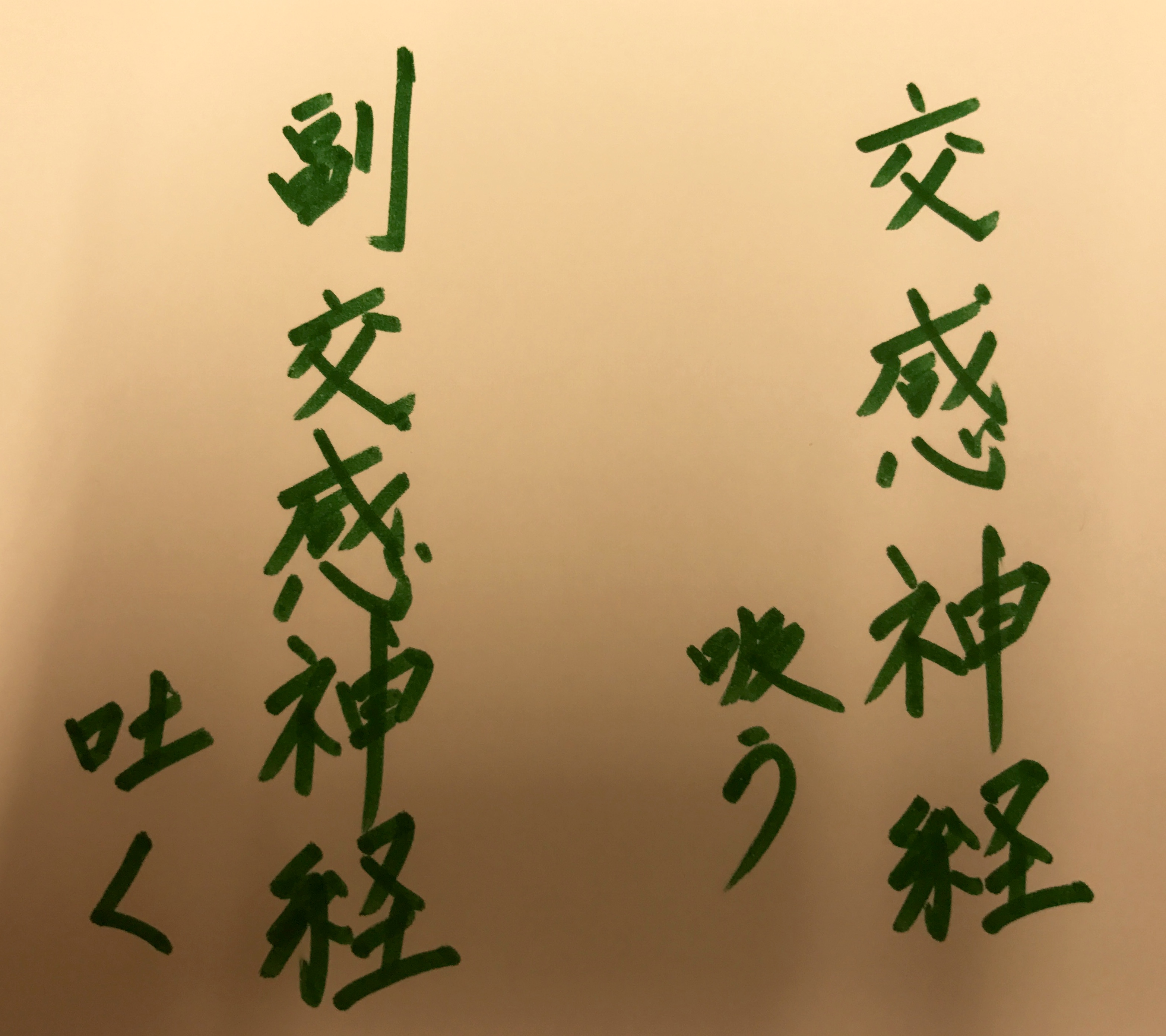
最近のコメント