
(東慶寺の紅白梅)
都会での生活は便利な反面、自然とは対極にある人工的な空間で過ごす時間が多く、気が枯れてくる(気枯れ・穢れ)感覚に陥るときがあります。人間も自然の一部ですから、自然とのバランスを適度にとることが心身のエネルギー維持にはとても大切です。
さて、自然の気をさっとチャージして体内に強い気を取り戻したい時は比較的アクセスのいい北鎌倉の地によく足を運びます。東京から電車で向かうと、大船駅と北鎌倉駅の中間を越えたあたりからまず気が変わります。写真の東慶寺は北鎌倉駅から徒歩1分ほどの地にある尼寺で、境内の後醍醐天皇皇女の墓所の辺りからさらに気が変わります。朝の静謐な空気を吸い、美しい花々を愛でているうちに体内にいい気が流れ込んでくるのを感じます。

(相模湾と建長寺を眼下に)
東慶寺をあとにして自然散策に。
普段はアスファルトが邪魔をして地のエネルギーを得ることはなかなかむつかしいのですが、自然の土の上を歩くと直接地のエネルギーをいただきやすく、鎌倉の地はそういう点においてもおすすめです。
時々歩く天園ハイキングコースは全長約4kmのゆるやかな散歩コースです。通称あじさい寺ともいう明月院の脇から、もしくは、建長寺境内からハイキングコースにつながっています。

(富士見台から望む冠雪の霊峰富士)
「山は癒やし、海は浄化」とも言われますが、この地は山と海の両方のエネルギーを身近に感じることができることも魅力のひとつです。歩いた後、海のエネルギーを取り入れたければ、材木座や由比ヶ浜、余裕あれば長谷の方まで足を運び、裸足になって砂浜を歩くのも自然からの良質なエネルギーをいただけます。
冒頭にも述べた「人間も自然の一部ですから、自然とのバランスを適度にとること」とは、「中庸である」ということです。ストレスや気の状態は目に見えないものだけに、いまどういう状態であるかということに自ら気づける習慣を取り入れることが長期的にコンディションを良好に維持するための解決策ではないか、と思っています。
くどいようですが、人間も自然の一部です。時には心身を自然の中に放牧させてあげましょう。

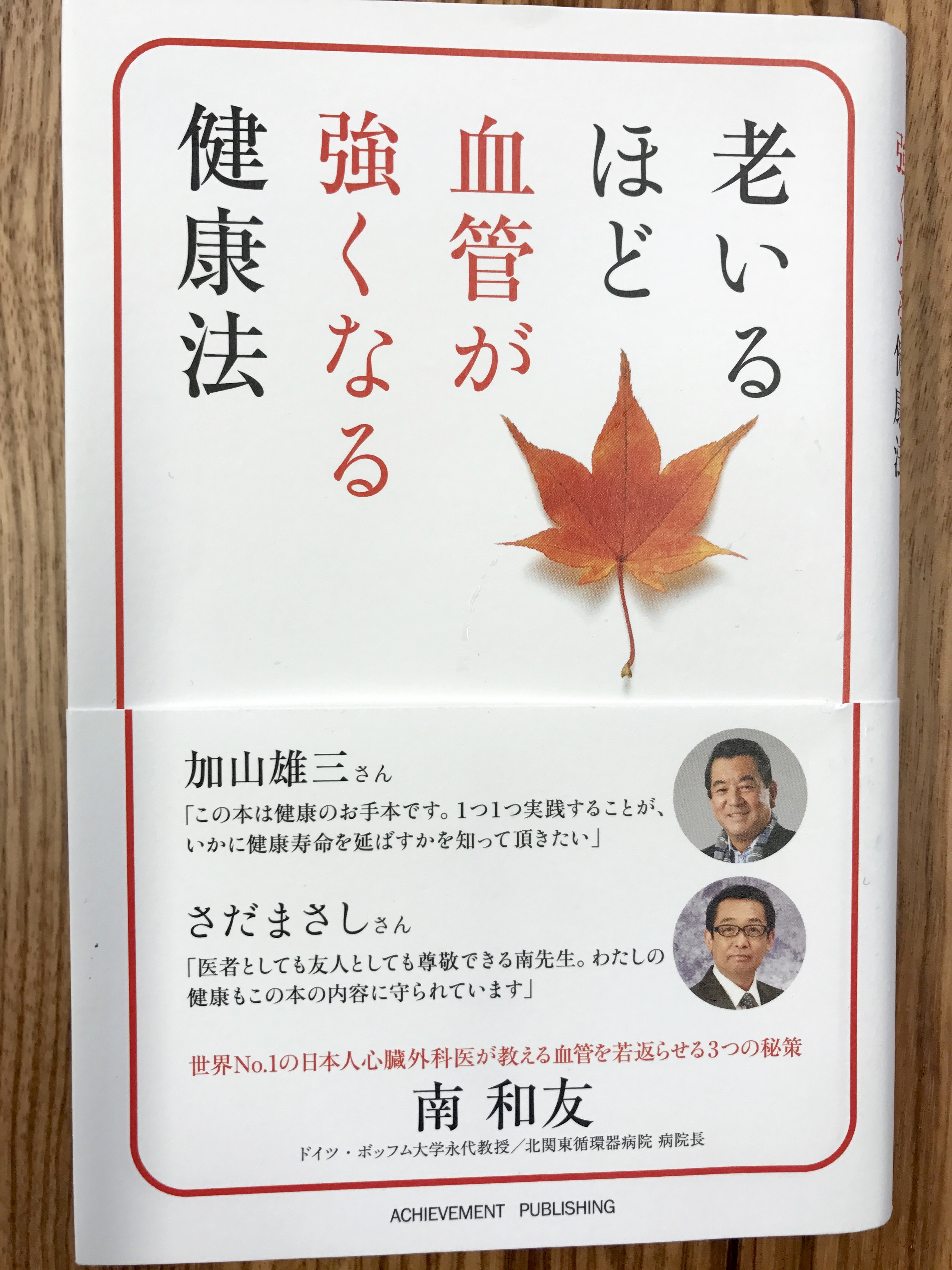
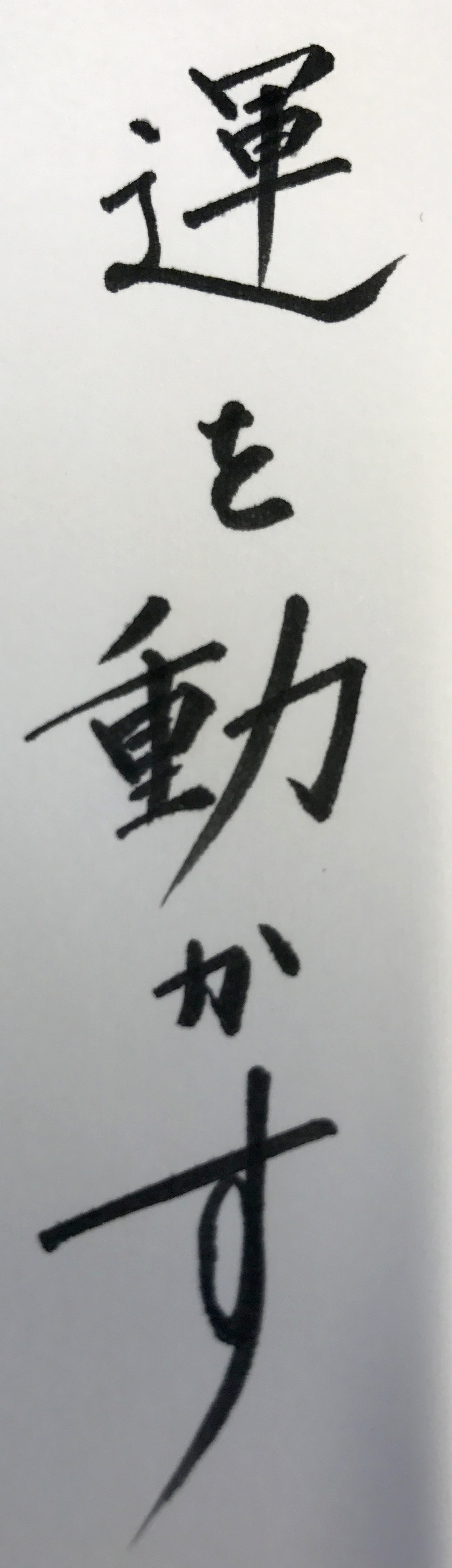
最近のコメント